相続手続きを自分でやるべきか悩んでいませんか?
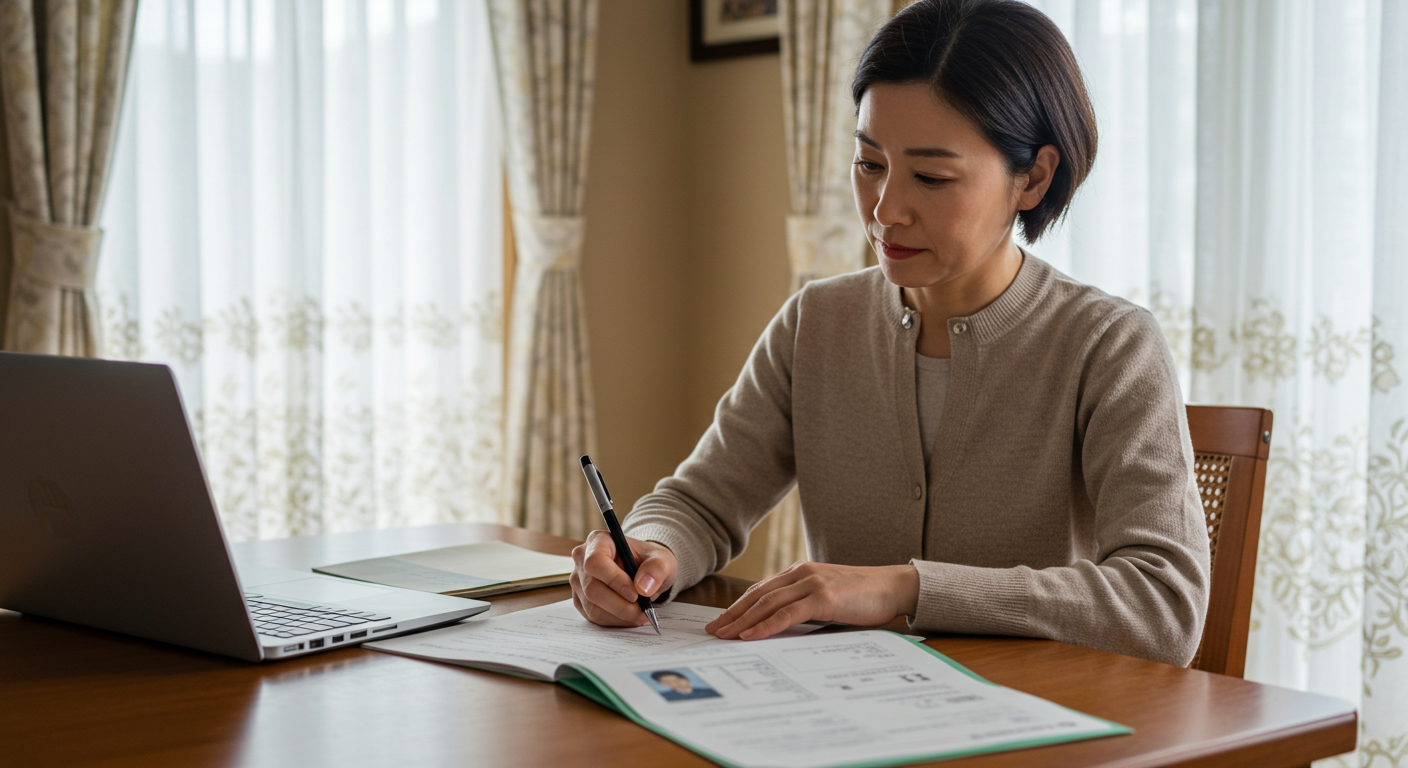
大切な家族を亡くし、悲しみの中で相続手続きという初めての経験に直面するのは本当に大変なことです。
「専門家に頼むと費用がかかるけど、自分でやるのは複雑そう…」とお悩みのあなたの気持ちはよく分かります。
この記事では、相続手続きを自分で行う方法と注意点を分かりやすく解説します。
専門知識がなくても一歩ずつ進められるよう、実践的なアドバイスをご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
相続手続きを自分でやるメリットとデメリット
相続手続きを自分でやるか専門家に依頼するか、その判断の前にメリットとデメリットをしっかり理解しておきましょう。
自分で相続手続きをするメリット
まず何といっても費用面のメリットが大きいです。
専門家に依頼すると、相続財産の規模や複雑さによりますが、数十万円から場合によっては百万円以上かかることもあります。
自分で手続きをすれば、この費用をかなり抑えられます。
それから、自分で手続きを進めることで相続の全体像を把握できるというメリットもあります。
亡くなった方の財産状況や関連書類を自分の目で確認することで、思わぬ発見があることも。
「父が大切にしていた山林があったなんて知らなかった」なんてケースもよくあるんですよ。
あと、意外と見落としがちなのが、自分のペースで進められるという点。
仕事の合間や休日を使って少しずつ進めることができます。
自分で相続手続きをするデメリット
でも正直言って、デメリットもあります。
何と言っても時間と労力がかかります。
初めての方だと、どこに何を提出すればいいのか調べるだけでも一苦労。
書類を集めるために何度も役所に足を運ぶことになりますし、金融機関も複数回訪問することになるでしょう。
それから専門知識がないと、思わぬところで躓くことも。

特に不動産や株式などの評価方法、相続税の計算など、専門的な知識が必要な場面では判断に迷うことが多いです。
私の知人も「自分でやろう」と意気込んでいたのに、途中で専門家に助けを求めることになりました。
最大のリスクは、手続きの漏れや誤りによる将来的なトラブルです。
期限を過ぎてしまったり、必要な手続きを忘れたりすると、あとから大きな問題になることも。
特に相続税の申告ミスは、追徴課税などのペナルティにつながる可能性があります。
相続手続きの基本的な流れ
相続手続きは大きく分けると以下のような流れになります。一つずつ見ていきましょう。
死亡届の提出(亡くなってから7日以内)
まず最初にやるべきことは死亡届の提出です。
これは亡くなった日から7日以内に、亡くなった方の本籍地か死亡地の市区町村役場に提出する必要があります。
死亡届には医師の死亡診断書が必要で、通常は病院で亡くなった場合は病院が用意してくれます。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医や救急で来た医師に作成してもらうことになります。
届出人は同居の親族が一般的ですが、同居していない親族や同居人でも構いません。
ただ、この段階ではまだ「相続手続き」というより「死亡の事実を届け出る手続き」という位置づけです。
遺言書の確認
次に確認すべきは遺言書の有無です。遺言書があると相続手続きの進め方が大きく変わってきます。
遺言書が自宅で見つかった場合、それが自筆証書遺言であれば、法務局での「遺言書保管制度」を利用していない限り、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
公正証書遺言の場合は、作成した公証役場で原本を保管しているので、そちらに確認しましょう。
遺言書の内容に従って相続を進める場合は、遺産分割協議が不要になるケースが多いため、手続きがスムーズになることが多いです。
ただ、遺言書の内容に不満がある相続人がいると、遺留分侵害額請求などの問題が生じることもあります。
相続人と相続財産の調査
遺言書の有無にかかわらず、誰が相続人になるのか、また被相続人(亡くなった方)がどのような財産を持っていたのかを調査する必要があります。
相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要です。
市区町村役場で取得できますが、本籍地が転々としていた場合は複数の役場から取り寄せることになり、これがなかなか手間です。
相続財産の調査は、預貯金、不動産、株式、保険、借金など多岐にわたります。
被相続人の自宅を探したり、通帳や証書を確認したりするほか、金融機関に問い合わせることも必要です。
ただし、金融機関は相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)がないと情報を開示してくれないことが多いので注意が必要です。
うちの父が亡くなった時は、思いもよらない銀行に口座があって、通帳も見つからず、偶然父の古い手帳から銀行名を見つけて問い合わせたことがありました。
こういう地道な調査が必要になることも覚悟しておきましょう。
遺産分割協議(遺言書がない場合)
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が必要です。
法定相続分(民法で定められた相続割合)通りに分けることもできますが、相続人の事情に応じて柔軟に分割することも可能です。
例えば、「長男は実家の不動産を相続し、次男と長女は預貯金を相続する」といった具合に、相続財産の種類によって分け方を工夫することもできます。
協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。
これは相続人全員が署名・押印する必要があり、後々のトラブル防止のため、内容は具体的かつ明確にしておくことが大切です。
各種名義変更手続き
相続人が確定し、遺産分割の方法が決まったら、いよいよ具体的な名義変更手続きに入ります。
預貯金の名義変更は各金融機関で行います。
必要書類は金融機関によって若干異なりますが、一般的には相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本、遺産分割協議書などが必要です。
不動産の名義変更は法務局で行う「相続登記」の手続きが必要です。
これは法改正により2024年から義務化され、期限内(相続を知った日から3年以内)に申請しないとペナルティが課される可能性があるので注意が必要です。
株式や投資信託などの有価証券も、証券会社や投資信託会社での名義変更手続きが必要です。
相続税の申告と納付(必要な場合)
相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。
申告期限は被相続人が亡くなった日から10か月以内と決まっています。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
相続財産がこれを超えると申告が必要です。
相続税の計算は複雑で、財産の評価方法や各種特例の適用など専門的な知識が必要になることが多いです。

自分で申告書を作成するのは正直かなりハードルが高いので、税理士に依頼することも検討した方がいいでしょう。
相続手続きを自分でやる際の注意点
相続手続きを自分でやる場合、特に注意すべきポイントをいくつか紹介します。
期限のある手続きを優先する
相続手続きには期限が設けられているものがあります。特に注意すべきは以下の手続きです。
・死亡届:死亡から7日以内
・相続税の申告・納付:死亡から10か月以内
・相続登記:相続を知った日から3年以内(2024年から義務化)
・生命保険の死亡保険金請求:各保険会社の約款による(通常3年程度)
期限を過ぎると、追徴課税やペナルティが発生する可能性があるので、カレンダーに期限を書き込むなど管理を徹底しましょう。
必要書類の収集と管理
相続手続きでは多くの書類が必要になります。主な書類は以下の通りです。
・戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の住民票除票
・固定資産税評価証明書(不動産がある場合)
・預貯金の残高証明書
・株式や投資信託の評価額証明書
これらの書類は複数の手続きで使い回すことが多いので、原本とコピーを分けて整理しておくと便利です。
書類ごとにクリアファイルを用意して管理するようにしましょう。
専門的な判断が必要な場面の見極め
自分でやるといっても、全てを自分だけで完結させる必要はありません。
専門的な判断が必要な場面では、専門家に部分的に相談するという方法もあります。
特に以下のような場合は専門家の力を借りた方が安全です。
・相続税の申告が必要な場合
・不動産の評価が難しい場合(貸地・貸家、事業用不動産など)
・相続人間で遺産分割について意見が対立している場合
・相続放棄や限定承認を検討している場合
・外国に財産がある場合
「ここだけ教えてほしい」という部分的な相談に応じてくれる専門家も増えているので、上手に活用しましょう。
相続手続きで困ったときの相談先
自分で相続手続きを進めていて行き詰まったとき、どこに相談すればよいのでしょうか。状況別に相談先を紹介します。
無料で相談できる公的機関
まずは無料で相談できる公的機関を活用しましょう。
・法テラス:法律相談全般(収入等の条件あり)
・各自治体の無料法律相談:弁護士による相談(予約制が多い)
・税務署の税務相談:相続税に関する一般的な相談
・法務局:不動産登記に関する相談
・家庭裁判所:遺言書の検認、相続放棄などの手続き相談
これらの機関では一般的な説明や手続きの案内をしてくれますが、個別具体的なアドバイスまでは期待できないことが多いです。
それでも、まずはどんな手続きが必要かの全体像を把握するのに役立ちます。
専門家への相談
より具体的なアドバイスが必要な場合は、専門家への相談を検討しましょう。
・弁護士:相続トラブル、遺言書の解釈、遺産分割協議など法律問題全般
・司法書士:不動産登記、相続手続き全般のサポート
・税理士:相続税の申告、財産評価
・行政書士:遺言書作成、各種許認可手続き
最近は初回無料相談を実施している事務所も多いので、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。
複数の専門家に相談して比較検討することも大切です。
相続相談サービスの活用
近年は相続に特化した総合的な相談サービスも増えています。
これらのサービスでは、相続手続き全般をワンストップでサポートしてくれるため、自分で手続きを進めながらも、分からない部分だけ相談するという使い方ができます。
相続相談サービスの特徴は、複数の専門家(弁護士、税理士、司法書士など)がチームで対応してくれることが多い点です。
相続は法律、税金、不動産など様々な分野にまたがる問題なので、総合的なサポートが受けられるのは心強いですね。
初回相談は無料のところが多く、その後は必要な部分だけピンポイントでサポートを依頼することも可能です。
「全部自分でやるのは不安だけど、専門家に全て任せるほどではない」という方にぴったりのサービスと言えるでしょう。
相続相談サービスを選ぶ際のポイントは、実績や口コミ、料金体系の透明性、相談のしやすさなどです。
複数のサービスを比較して、自分に合ったところを選びましょう。
相続手続きを自分でやる人のための実践的アドバイス
最後に、相続手続きを自分でやろうと決めた方のための実践的なアドバイスをいくつか紹介します。
チェックリストを作成して進捗管理
相続手続きは多岐にわたるため、何をやったか、何をこれからやるべきかを管理するチェックリストを作成しておくと便利です。
エクセルなどで作成して、期限や必要書類も一緒に記録しておくとよいでしょう。
手続きごとに「準備中」「申請中」「完了」などのステータスを色分けして管理すると、全体の進捗が一目で分かるので便利です。
相続人間のコミュニケーションを大切に
相続では相続人間のコミュニケーションが非常に重要です。
特に遺産分割協議では、お互いの希望や事情を丁寧に聞き合うことが円満解決の鍵となります。
定期的に進捗を共有する機会を設けたり、重要な決断の前には全員で話し合いの場を持ったりすることをおすすめします。
メールやLINEなどでグループを作っておくと、情報共有がスムーズになります。

ただ、文字だけのやり取りは誤解を生みやすいので、重要な話し合いは直接会って、または少なくともビデオ通話で行うようにしましょう。
記録を残す習慣をつける
相続手続きは長期間にわたることが多いため、いつ、どこで、誰と、何を話したか、どんな手続きをしたかの記録を残しておくことが重要です。
例えば、金融機関に問い合わせた際の担当者名や回答内容、提出した書類の控えなどを日付とともにノートやデジタルツールに記録しておくと、後から「あれ?あの手続きどうなったっけ?」と迷うことがなくなります。
手帳に加えて、スマホのメモアプリも活用するのがオススメです。
写真も一緒に保存できるので、提出した書類の控えなども一元管理できるので役立ちます。
相続手続きの専門家に依頼するべきケース
ここまで自分で相続手続きを進める方法を紹介してきましたが、正直なところ、専門家に依頼した方がよいケースもあります。以下のような場合は、専門家への依頼を真剣に検討しましょう。
複雑な相続財産がある場合
以下のような複雑な財産がある場合は、専門家のサポートが必要になることが多いです。
・事業用資産(会社の株式、事業用不動産など)
・海外に所在する財産
・著作権や特許権などの知的財産権
・複雑な不動産(共有持分、借地権、底地権など)
・多額の負債がある場合
特に事業承継が絡む相続は、会社の存続にも関わる重要な問題なので、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
相続人間で意見の対立がある場合
相続人同士の関係が良好でない場合や、遺産分割について意見が対立している場合は、中立的な立場の専門家に間に入ってもらうことで、感情的な対立を避けながら話し合いを進めることができます。
特に、以下のような場合は専門家の力が必要です。
・相続人の中に疎遠になっている人がいる
・前妻の子どもと後妻の子どもなど、複雑な家族関係がある
・特定の相続人が被相続人の生前に多額の援助を受けていた
・認知症など判断能力に不安のある相続人がいる
時間的余裕がない場合
仕事や育児、介護などで忙しく、相続手続きに十分な時間を割けない場合も、専門家への依頼を検討すべきです。
特に相続税の申告期限(10か月)が迫っている場合は、専門家のサポートを受けることで、期限内に適切な対応ができます。
「自分でやりたい」という気持ちは大切ですが、時間不足によるミスや漏れが発生すると、後々大きな問題になることもあります。自分の状況を冷静に判断して、必要なサポートを受けることも大切です。
まとめ:相続手続きを自分でやるか専門家に依頼するか
相続手続きを自分でやるか専門家に依頼するかは、相続財産の複雑さ、相続人間の関係性、自分の時間的余裕などを総合的に判断して決めるべきです。
自分でやることで費用を抑えられる一方、時間と労力がかかり、専門知識不足によるリスクもあります。専門家に依頼すれば安心感がある反面、費用がかかります。
最近は「一部だけ専門家に依頼する」という中間的な選択肢も増えています。
例えば、相続税申告だけ税理士に、不動産登記だけ司法書士に依頼するなど、自分の不安な部分だけサポートを受けるという方法です。
相続相談サービスでは、初回無料相談を通じて自分の相続がどの程度複雑かを判断する材料を得ることができます。
まずは相談してみて、「これなら自分でできそう」「ここだけ手伝ってほしい」といった判断をするのもよいでしょう。
大切なのは、「全部自分でやらなければならない」と思い込まず、必要に応じて専門家の力を借りる柔軟さを持つことです。
相続は一生に何度も経験するものではありません。不安を抱えたまま無理をするより、適切なサポートを受けながら進めることで、故人の遺志を尊重した円満な相続を実現しましょう。
相続手続きに不安を感じたら、まずは相続相談サービスに問い合わせてみてください。初回無料相談を通じて、あなたの状況に合った最適な進め方が見えてくるはずです。

