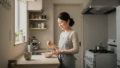相続手続きの不安、税理士への依頼を迷っていませんか?

大切な家族を亡くされた後の相続手続き。
何から始めればいいのか分からず、不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
税理士への依頼を考えても「費用がどれくらいかかるのか」「相場はどのくらいなのか」という疑問をお持ちの方も多いと思います。
この記事では、税理士に相続手続きを依頼する際の費用相場について、初めての方にも分かりやすくご説明します。
相続の不安を少しでも和らげるお手伝いができれば幸いです。
税理士に相続手続きを依頼するメリット
相続手続きを自分でやろうと思うと、想像以上に複雑で時間がかかるものです。
私も親戚の相続で関わったことがありますが、書類の山と格闘した記憶があります。
税理士に依頼することで得られる主なメリットをご紹介します。
まず何より、専門知識を持つプロに任せることで「正確な手続き」が期待できます。
相続税の申告ミスは追徴課税のリスクがありますから、これは大きな安心感につながります。
また、重要なのが「節税対策」です。
適切な財産評価や各種特例の適用により、合法的に税負担を軽減できる可能性があります。
素人ではなかなか気づけない部分ですね。
それから、相続手続きにかかる「時間と労力の節約」も大きなメリットです。
相続発生後は精神的にも疲れている時期。

煩雑な手続きから解放されることで、大切な故人を偲ぶ時間や、家族との関係修復に集中できます。
税理士に依頼する相続手続きの費用相場
「でも実際いくらかかるの?」というのが一番気になるところですよね。
税理士に相続手続きを依頼する際の費用相場を、サービス内容別にご説明します。
相続税申告の基本報酬
相続税申告の基本報酬は、相続財産の総額や複雑さによって大きく変わります。一般的な相場としては、以下のような金額が目安になります。
・相続財産5,000万円未満の場合:20万円〜40万円程度
・相続財産5,000万円〜1億円の場合:30万円〜60万円程度
・相続財産1億円〜3億円の場合:50万円〜100万円程度
・相続財産3億円以上の場合:100万円〜
ただし、これはあくまで目安です。
相続人の数が多い場合や、不動産や事業用資産など評価が難しい財産がある場合は、さらに高額になることもあります。

「うちはそんなに財産がないから関係ないかも」と思われるかもしれませんが、実は土地や建物の評価額が予想以上に高く、思わぬ相続税が発生するケースもよくあるので、一度税理士に相談する事をオススメします。
相続税の申告が不要な場合の費用
「うちは相続税の申告は必要ないかも」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下の財産であれば、相続税の申告は不要です。
しかし、申告が不要かどうかの判断自体が難しいこともあります。
この判断を含めた相談だけなら、多くの税理士事務所では初回無料相談を実施しています。
申告不要と判断された場合でも、遺産分割協議書の作成や各種名義変更手続きなどが必要になることがあります。
こうした場合の費用相場は以下の通りです。
・遺産分割協議書の作成:5万円〜15万円程度
・不動産の名義変更手続き:1物件あたり3万円〜10万円程度
・預貯金の名義変更手続き:1口座あたり1万円〜3万円程度
相続税申告以外の付随業務の費用
相続手続きには、税務申告以外にもさまざまな業務があります。
これらの付随業務にかかる費用相場も知っておくと安心です。
・相続関係説明図の作成:2万円〜5万円程度
・財産目録の作成:5万円〜20万円程度
・生前対策の相談・提案:10万円〜30万円程度
・相続時精算課税制度の申告:10万円〜20万円程度
これらの費用は事務所によって大きく異なりますし、パッケージ料金として一括で提示されることも多いです。
見積もりをもらう際は、どの業務が含まれているのかをしっかり確認することが大切です。
税理士費用の決まり方と見積もりのポイント
「なんだか費用の幅が広すぎて、結局いくらかかるのか分からない…」と思われたかもしれません。
実は、税理士費用が決まる要素にはいくつかのポイントがあります。
費用に影響する主な要素
税理士費用に影響する主な要素は以下の通りです。
1. 相続財産の総額と内訳
財産が多いほど、また不動産や自社株など評価が難しい財産があるほど高額になります。
2. 相続人の人数と関係性
相続人が多いほど、また相続人間で意見が分かれているケースほど業務量が増えて費用が上がります。
3. 事業承継の有無
事業用資産の評価や各種特例の適用など、専門性の高い業務が増えると費用も高くなります。
4. 生前対策の有無
生前からの対策を含めると、長期的なサポートになるため費用も変わってきます。
5. 税理士事務所の規模や所在地
大手事務所や都心の事務所は、一般的に地方や小規模事務所より費用が高い傾向にあります。
見積もりを取る際のチェックポイント
複数の税理士事務所から見積もりを取る際は、以下のポイントをチェックすると良いでしょう。
・基本報酬に含まれる業務範囲は何か
・追加で発生する可能性のある費用はあるか
・着手金と成功報酬の内訳はどうなっているか
・相談料や打ち合わせ費用は別途かかるのか
・交通費や実費はどう計算されるのか

見積書だけでなく、契約書や報酬規程もしっかり確認することをおすすめします。「思ったより高かった」というトラブルを避けるためにも大切なステップです。
税理士選びで失敗しないためのポイント
「費用相場は分かったけど、どうやって良い税理士を見つければいいの?」という疑問にお答えします。
単に費用の安さだけで選ぶのはあまりおすすめできません。
相続税に強い税理士の見分け方
税理士といっても得意分野は様々です。相続税に強い税理士を見分けるポイントをご紹介します。
・相続税申告の実績が豊富か
・相続専門のチームや部署があるか
・税務署での勤務経験があるか
・相続関連の執筆や講演活動をしているか
・弁護士や司法書士など他の専門家とのネットワークがあるか
特に相続は税務だけでなく、法律や不動産、時には家族間の調整など多岐にわたる知識が必要です。
総合的なサポートができる税理士を選ぶことが大切です。
初回相談で確認すべきこと
多くの税理士事務所では初回無料相談を実施しています。
この機会に以下の点を確認しておくと良いでしょう。
・相続税申告の必要性の有無
・概算の相続税額
・申告期限までのスケジュール
・必要な書類や準備すべきこと
・費用の見積もりと支払い方法
・担当者の経験や実績
また、初回相談での対応や説明の分かりやすさも、税理士選びの重要なポイントです。
「なんとなく話しづらい」と感じたら、別の税理士も検討してみることをおすすめします。
自分で相続手続きをする場合と税理士に依頼する場合の比較
「やっぱり費用がネックで、自分でやりたいけど不安…」という方も多いと思います。
ここでは、自分で手続きをする場合と税理士に依頼する場合のメリット・デメリットを比較してみましょう。
自分で相続手続きをする場合
【メリット】
・費用を抑えられる
・自分のペースで進められる
・相続の全体像を把握できる
【デメリット】
・専門知識がないと時間がかかる
・申告ミスのリスクがある
・見落としによる節税機会の損失
・精神的・時間的な負担が大きい
自分で手続きをする場合は、税務署の無料相談や国税庁のホームページなどを活用すると良いでしょう。
ただし、財産が複雑だったり、相続人間で意見が分かれていたりする場合は、専門家への依頼を検討した方が安心です。
税理士に依頼する場合
【メリット】
・専門知識による正確な申告
・節税対策の提案が期待できる
・時間と労力の節約
・トラブル発生時のサポート
・精神的な安心感
【デメリット】
・費用がかかる
・資料収集などの手間は自分でする必要がある
・税理士によってサービス内容や質にばらつきがある

税理士に依頼する場合でも、財産目録の作成や必要書類の収集など、ご自身で行う作業もあります。
どこまでを税理士に依頼し、どこまでを自分で行うかを事前に確認しておくことが大切です。
相続手続きで多い失敗例と対処法
相続手続きでよくある失敗例と、その対処法についてご紹介します。
これらを知っておくことで、自分で手続きをする場合も税理士に依頼する場合も、スムーズに進めることができるでしょう。
期限切れによる加算税のリスク
相続税の申告期限は、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
この期限を過ぎると、無申告加算税(15%〜20%)や延滞税が課されることになります。
対処法としては、まず期限を正確に把握し、余裕をもったスケジュールを立てることが大切です。
また、期限内に申告が難しい場合は、税務署に相談して「申告期限の延長申請」を行う方法もあります。
財産の見落としによるトラブル
「あとから預金が見つかった」「知らなかった不動産があった」など、財産の見落としは意外と多いものです。
これが原因で相続人間のトラブルに発展したり、税務調査で指摘されたりするケースもあります。
対処法としては、被相続人の通帳や印鑑、保険証書、不動産関係書類などを丁寧に確認することが基本です。
また、「法定相続情報証明制度」を利用して、金融機関や役所での調査をスムーズに行うことも有効です。
相続人間の認識の違いによる紛争
「遺言書の解釈が違う」「生前贈与の有無について意見が分かれる」など、相続人間の認識の違いから紛争に発展するケースも少なくありません。
対処法としては、早い段階から相続人全員が参加する話し合いの場を設けることが大切です。
また、中立的な立場の専門家(税理士や弁護士)に間に入ってもらうことで、感情的な対立を避けることができます。
相続手続きを安心して任せられる相談先
「自分でやるのは不安だけど、誰に相談したらいいの?」という方のために、相続手続きの相談先をご紹介します。
専門家への相談方法
相続手続きの専門家には、税理士のほかにも以下のような選択肢があります。
・弁護士:遺産分割や相続トラブルの法的解決に強み
・司法書士:不動産の名義変更や相続登記に強み
・行政書士:遺言書作成や各種申請手続きに強み
・信託銀行:財産管理や遺言執行に強み
それぞれ得意分野が異なるため、自分の状況に合った専門家を選ぶことが大切です。
最近では、これらの専門家がチームを組んでワンストップサービスを提供する「相続相談センター」なども増えています。
無料相談サービスの活用法
費用面で不安がある方は、まず無料相談サービスを活用してみましょう。
・税理士会の無料相談会
・法テラスの法律相談
・自治体の相続相談窓口
・金融機関の相続相談サービス
これらの無料相談で全てを解決するのは難しいかもしれませんが、自分の状況を整理し、今後の方針を決める良い機会になります。
また、多くの税理士事務所では初回無料相談を実施しています。
複数の事務所の無料相談を利用して比較検討するのも一つの方法です。
相続手続きを始める前に知っておきたいこと
最後に、相続手続きを始める前に知っておきたい基本的なことをまとめます。
必要な書類と入手方法
相続手続きに必要な主な書類は以下の通りです。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・不動産の登記簿謄本
・預貯金の残高証明書
・有価証券の評価証明書
・生命保険の支払証明書
・被相続人の確定申告書の控え
これらの書類は、市区町村役場、法務局、金融機関、保険会社などで取得できます。
ただし、取得には手数料がかかるものもありますし、亡くなった方との関係を証明する書類が必要な場合もあります。
相続税の基礎知識
相続税について、最低限知っておきたい基礎知識をご紹介します。
・基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
・税率:10%〜55%の累進課税
・申告期限:被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
・主な特例:小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など
特に「小規模宅地等の特例」は、自宅や事業用の土地について最大80%評価減が受けられる重要な特例です。
条件を満たせば大幅な節税が可能になりますので、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ:相続手続きの不安を解消するために
相続手続きは誰にとっても初めての経験であることが多く、不安を感じるのは当然のことです。
税理士への依頼費用は決して安くはありませんが、正確な申告による安心感や、適切な節税対策によるメリットを考えると、専門家への依頼を検討する価値は十分にあります。
特に以下のような場合は、専門家への相談をおすすめします。
・相続財産が基礎控除額に近いか超えている
・不動産や事業用資産など評価が難しい財産がある
・相続人が多いまたは遠方に住んでいる
・相続人間で意見が分かれている
・被相続人に生前贈与や債務がある
まずは無料相談を活用して、自分の状況を整理してみることから始めてみてはいかがでしょうか。
「この記事を読んで少し不安が和らいだ」という方がいらっしゃれば、とても嬉しく思います。
相続は財産の引き継ぎだけでなく、故人の想いや家族の絆を次世代につなぐ大切な機会でもあります。
専門家のサポートを受けながら、穏やかな気持ちで相続手続きを進められることを願っています。
不安や疑問がある方は、ぜひ専門の相続相談サービスにお問い合わせください。